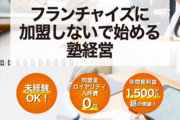レンタカー事業の開業の流れと申請方法、保険加入など

「車は持っていないけれど運転免許は持っているので、たまの買い物や旅行のときに車を運転したい」「旅先で車を借りてドライブしたい」など、レンタカーが役に立つ場面は意外に多いものです。
そのため、レンタカー事業も上手に運営すれば、十分に収益が見込めます。
レンタカー事業とは有償で自動車を貸渡す事業のことをいいますが、難しい日本語を使うと「自家用自動車有償貸渡業」と呼ばれます。
なお、レンタカー事業は道路運送法という法律に基づく許可が必要となるため、手続きをいい加減に行ったのでは、許可が下りない可能性がある点に注意しましょう。
ここでは、レンタカー事業を開業する場合に必要な手続きや流れ、申請書類などを中心に解説していきます。
1
レンタカー事業には法律に基づく手続きが必須
車を所有している限り、毎月の自動車ローンの支払いや駐車場代、車検代、税金など一定の費用が発生します。 そのため、「自動車は必要なときに使えれば十分だから、なるべく費用はかけたくない」という人が増えています。 それがレンタカーの需要が増えている背景になっているといわれています。 そのような合理的な消費者に、事業者が20~30万円で安く仕入れた中古車を貸し付け、年間で1台あたり80~100万円程度の収入を得るのも可能となっています。 つまり、レンタカー事業は低コストかつ高収益な状況が発生しているため、上手に運営すれば事業として成功しやすいのが実情です。
しかし、どんな車でもレンタカー事業に使えるわけではありません。 日本では、道路運送法という法律で、国土交通大臣の許可がなければレンタカー事業を営んではいけない決まりになっています(道路運送法80条1項)。 具体的には、レンタカー事業を開業するにあたり、まず、国土交通大臣に「自家用自動車有償貸渡業」の許可を申請しなくてはいけません。 この申請が通れば、レンタカー事業に使うための車両を登録し、ナンバーを交付してもらうことができます。 なお、レンタカー事業に使う車に交付されるナンバーは「わ」に統一されているのも大きな特徴です。
2
レンタカー事業の具体的な開業の流れは?
ここで、レンタカー事業の開業の流れについて押さえておきましょう。 まず、申請者は国土交通省の最寄りの運輸支局に許可申請書を提出し、審査が行われます。 審査から許可までの期間はおおよそ1カ月です。 許可証が交付されると、登録免許税(9万円)を納めます。
その後、レンタカー事業に使う車両のナンバーを「わ」にするための変更登録を行います。 なお、申請にあたっては、欠格事由や申請者及び役員の要件、自動車の種類に関する規定に触れていないか確認しましょう。 まず、欠格事由ですが、代表例としては1年以上の服役または禁固の刑に処せられており、その執行が終わってから、または執行猶予期間が終了してから2年を経過していない場合があげられます。
また、申請者及び役員は、申請日より前の2年間で無許可タクシーやナンバー貸しなど、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないことが必要です。 また、レンタカー事業に利用できる自動車は、自家用自動車、要件を満たす自家用マイクロバス、自家用トラック、特殊用途自動車、二輪車の5種類です。
3
自家用自動車有償貸渡業の申請に必要な書類は?
運輸支局に許可申請を行うにあたっては、いくつかの書類が必要になります。
まず、所定の「許可申請書」を用意します。 運輸支局のホームページからダウンロードするか、直接窓口に出向いて入手しましょう。 「貸渡料金表及び貸渡約款」は、レンタカー事業での車種ごとの利用料や貸出上のルールについてまとめたものです。 申請者が作成し、提出します。 「確認書」は、申請にあたっての欠格事由に該当しないことを確認するためのものです。 「事務所別車種別配置車両数一覧表」とは、レンタカー事業の各事業所に配置されている車について、車種と台数をリスト化したものです。
さらに、保険の加入状況や加入計画、警備管理者の配置計画などを取りまとめ、「貸渡しの実施計画書」として提出します。
加えて、会社の場合は法人の登記簿謄本、個人の場合は住民票も必要です。 これらの書類が全部そろったら、窓口に出向くか、郵送で運輸支局に提出しましょう。
なお、郵送で提出する場合は、書類に不備があったときに備えて連絡先を書いたメモを同封しておくとよいでしょう。
4
ドライバー保険への加入を義務付けること
レンタカー事業を営むにあたっては、利用者にも安全への意識を強く持ってもらうとともに、ドライバー保険への加入を義務付けましょう。 自動車保険の中には、「他車運転特約」など、レンタカーや他人の車を運転していた場合の事故であっても保障される特約が付帯できるものがあります。
しかし、利用者が全員そのような特約を付帯しているとは限りません。
さらに、車を所有していない人は、自動車保険自体にも加入していないのです。 通常の自動車保険はあまりあてにできないため、レンタカーでの事故であっても保障されるドライバー保険でカバーする必要があります。 貸渡約款の中に「ドライバー保険への加入を義務とする」旨の文言を盛り込んでもよいでしょう。
また、レンタカー事業を開業するにあたっては、複数の損保会社に相談し、レンタカーの運転でも保障してくれるドライバー保険を比較検討することをおすすめします。
可能であれば、ドライバー保険の商品説明パンフレットも事務所に設置し、受付のたびに利用者に交付するようにしましょう。
5
法人でスタートするメリットとは?
レンタカー事業を営むには、個人と法人のどちらが有利なのでしょう。 手間はかかりますが、やはり法人の方が有利といえます。 まず、法人化にあたっては登記が必須です。 登記することによって、「実在する会社」という証明ができるため、社会的信用が得られやすくなります。
また、信用が得られやすいということは、銀行の融資に通りやすいというメリットも生むのです。 さらに、法人化して赤字が出たとしても、赤字が出た年の翌年から最大9年間繰り越すことができます。 個人事業主でも赤字の繰り越しはできますが、赤字が出た年の翌年から最大3年間が限度です。
なお、自家用自動車有償貸渡業の許可は、各個人や法人に対して出される性質上、一度許可をとったら個人から法人に引き継ぐことはできません。 現在は資本金1円から会社設立が可能となっているため、会社設立時の費用を払ってでも法人からスタートすることを前向きに検討しましょう。
ただし、会社設立時には、登録免許税などの諸費用が20万円ほどかかります。
6
フランチャイズに加盟?メリット・デメリットを分析
レンタカー事業を開業する場合、大手レンタカーチェーンのフランチャイズに加盟する方法も考えられます。 この方法のメリットとしては、集客や車両の調達、トラブル対応などの業務フローが安定していることがあげられます。 初めてレンタカー事業を行うにしても、業務フローを守りながら、わからない点を本部に随時相談して進めていけるのは大きなメリットでしょう。
また、利用者にも、大手レンタカーチェーンの名前は「信頼できそう」という理由で好意的に受け取られます。 その結果、利用してもらえるのであれば、フランチャイズに加盟するメリットはあるでしょう。
一方、フランチャイズ本部に支払う加盟料が50万円ほどかかります。 そのため、ある程度まとまった開業資金(目安は90万円以上)が必要になる点がデメリットです。 また、フランチャイズ本部の意向に従う必要があるため、独自のアイデアを盛り込みにくいというデメリットもあります。
しかし、レンタカー事業は収益をあげる以前に、利用者の安全を守れる体制で運営することがはるかに重要なビジネスです。 独自のアイデアを前面に出すより、法制度や一定の業務フローを厳格に守るほうが、利用者の安全確保にはつながりやすいのも実情でしょう。
7
まとめ
実際にレンタカー事業での開業を目指す際は、運輸支局など、官公庁とのやり取りが非常に多くなります。 そのため、行政書士など、官公庁とのやり取りや手続きに習熟している専門家に依頼するとスムーズにいくでしょう。 自分でやるにしても、周囲の協力を得ながら、漏れのないように手続きを進めましょう。
また、車両の手入れや車内の清掃を徹底したり、事務所に返却に来た利用者に飲み物やお茶菓子を出したりなど、通常の業務フローに触れない部分のサービスやアイデアは積極的に盛り込みましょう。
もちろん、オフィスや駐車場など、利用者とのやり取りをする場所はいつもきれいに保つ必要があります。 利用者の心を動かすのは、実はそういった「さりげない気づかい」かもしれません。
フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す ビジェント
オススメの商材・サービスを集めてみました!
-
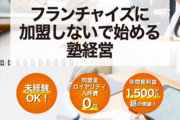
教育ICT「システムAssist」
-

Match助成金・補助金コンサルタント
-

お酒の美術館
-

レンスペ本舗
-

アイサポ
-

個別学習のセルモ
-

訪問鍼灸マッサージ「KEiROW」
-

地域密着型デイサ-ビス だんらんの家
-

スパイス研究所「MAD CHEFs」
-

大石久右衛門
-

就労継続支援B型事業所「スーパーチャレンジセンターミライ」
-

海鮮丼専門店「丼丸」
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015