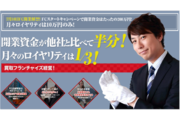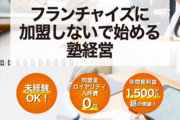独立開業後は確定申告が必要!確定申告の流れとは

独立開業すると自ら所得を計算して所得税の確定申告を行う必要があります。 会社員だった人は会社が年末調整で確定申告に相当する作業を代わりに行ってくれていましたので確定申告をしたことがないというケースも多いはずです。
そのため、どのように確定申告の対応をすればよいのかわからない人もいるでしょう。 確定申告をせずに納税義務を果たさないと延滞税や加算税などで余分な税負担が発生してしまうこともありえます。 事業経営とあわせて確定申告のための準備作業も欠かせません。
そこで、独立開業したあと必要となる確定申告書作成のためにはどんな作業が必要になるのか、事業所得の計算方法や確定申告の流れ、さらには提出期限などについて詳しくお伝えします。
1
独立開業すると確定申告義務が生じる
独立して個人事業主として開業したら、まずは事業を軌道に乗せることを優先させて仕事を進めることになるでしょう。
しかし、それだけに注力していると確定申告で苦労することになる可能性があります。
個人事業主は、事業が赤字になるなど一定の場合を除いて、原則として税金の確定申告が義務付けられています。
会社員は会社が税金に関する処理を代わりに行ってくれていましたが、個人事業主は自ら所得を計算して確定申告書を作成し、期限までに提出することが求められます。 納税金額が発生する場合は、申告期限までに税金の支払いも済ませる必要があります。
個人事業主が確定申告すべき税金は所得税と消費税です。
そのほかにも税負担は発生しますが、住民税や事業税については所得税の確定申告をすることで役所側が税額計算を行うことになりますので確定申告の必要はありません。
消費税については、特定の場合を除き、2年目までは納税義務が発生しません。
そのため、独立開業直後はまず所得税の確定申告ができるように準備しておく必要があるといえます。
2
確定申告の流れ
確定申告に対応できるようになるためには、まず確定申告の流れを理解しておくことが重要です。 所得税の確定申告を行うためには課税対象となる所得を把握する必要があります。 所得税は暦年課税となっています。
そのため、1月から12月の間に個人事業主が事業によって得た所得を把握することから始まります。 事業所得は総収入から必要経費を引いて求めます。
税法に従って帳簿を付ける場合は、事業所得は決算上の利益とほとんど同じものだと理解するとよいでしょう。 事業所得が計算できたら、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除を引いて課税総所得金額を求めます。
さらに課税総所得に対して超過累進税率を適用して所得税額を求めることになります。
超過累進税率とは所得金額が高くなると税率が上がる仕組みで、最低5%から最高45%に設定されています。 事業の所得以外に株式売却益などで申告の必要がある所得が発生している場合は、その所得も確定申告書に記載することになります。
計算結果を確定申告書に記載して税務署に提出するというのが確定申告の流れです。
3
確定申告書の提出方法と期限
個々の事業取引に関しては帳簿を付けて管理することになります。
領収書も保存義務がありますのでしっかり保管する必要があります。
1年間まとめて処理しようとすると「この領収書は何の支出だっけ」となり、思ったよりも大変な作業になる可能性があります。 個々の取引は発生した都度、帳簿記入を行うことがポイントです。
1年間の取引金額が集計できたら国税庁のホームページ上にある確定申告書作成コーナーを利用して確定申告書を作成することをおすすめします。 必要事項を入力すると税額計算を自動的に行ってくれますので便利です。
また、確定申告書のフォームで印刷できるメリットもあります。
一定の要件を満たせば電子申告によりネット上の処理を申告書作成から提出まで完結できますが、印刷したものを郵送で提出することも認められています。 郵送で提出する場合は控えを含めて2部提出し、返信用封筒に切手を貼って返送してもらうようにしましょう。 申告期限は翌年2月16日から3月15日までです。
納税金額が発生する場合は提出期限の末日である翌年3月15日までに納税する必要があります。
また、事業所得が赤字になるなど課税所得が発生しない場合は確定申告義務は生じません。 ただし赤字を翌年以降に繰り越して節税できる余地がありますので赤字でも確定申告しましょう。
4
総収入金額計算のポイント
確定申告書作成にあたっては事業所得を正確に計算することがポイントとなります。 正確な計算を行うためには帳簿を付ける必要があります。
パソコン上にインストールして使う会計ソフトやクラウド会計システムなどを使えば簿記の知識がなくても帳簿記入は簡単にできます。 事業所得を計算するうえで最も重要なポイントは総収入金額の計算です。 総収入金額とは事業の売上にあたるものだと理解するとよいでしょう。
商品を売った場合やサービスを提供した場合の報酬金額のことです。
総収入金額の計算にあたっては計上時期に注意しましょう。
総収入金額は、現預金を手にしたタイミングではなく商品を引き渡したタイミングやサービス提供が完了したタイミングで計上することになっています。
得意先が法人の場合は、月末締め翌月払いなどの取り決めになっていることが多いでしょう。
その場合は翌月の入金タイミングではなく締め日が含まれる月に総収入金額を計上することになります。
例えば、12月に商品を引き渡して翌年1月に代金をもらう場合は12月の売上となり、その年の総収入金額に計上して確定申告することが求められます。
5
必要経費計算のポイント
事業所得の計算にあたっては必要経費の計算も大切になります。
必要経費に関する主なポイントは2つあります。
1つは売上の場合と同様に、支出したタイミングで必要経費を計上するのではなく、消耗品などを手に入れたタイミングで計上することです。 現預金が動くタイミングではないことを理解しておきましょう。
2つ目は減価償却の理解です。 1年以上使用する設備や備品などは原則として減価償却と呼ばれる処理を行うことが求められます。 減価償却とは取得した固定資産の代金をそのまま取得年の必要経費に入れずに、使っている期間に分割して必要経費に計上する処理のことです。
例えば、100万円の設備を取得して5年間使用する場合、取得年から5年間、毎年20万円の必要経費を計上するということです。 使用年数は税法で定められたものを使います。
ただし、一定の個人事業主の場合は30万円未満の固定資産であれば取得年に一括して必要経費にできます。 30万円以上の固定資産を取得する場合は減価償却計算が求められることを知っておきましょう。
計算は面倒ですが会計ソフトを使えば簡単に計算できます。
6
確定申告するなら青色申告を
独立開業した場合は、税務署に対して個人事業を開業したという届を提出する必要があります。
そのとき同時に青色申告承認申請書も提出して青色申告者になることをおすすめします。 青色申告者になると複式簿記で記帳した帳簿に基づいて利益の計算書である損益計算書と財産の一覧表である貸借対照表を作成して確定申告書に添付することが義務付けられます。
その反面、税制上のメリットも得られます。 主なメリットとしては青色申告特別控除が利用できることがあげられます。 青色申告特別控除とは、事業所得の計算上65万円の控除が認められる制度です。
総収入金額から必要経費を引いた残額が65万円以下であれば、この青色申告特別控除を適用することで事業所得をゼロにすることができます。
その他にも一定の要件を満たせば家族従業員である青色事業専従者の給料を全額必要経費にできるなどのメリットもあります。 個人事業主は青色申告によって節税できることを理解しておきましょう。
7
まとめ
独立開業して個人事業主となった人は事業経営だけでなく確定申告にも対応する必要があります。 確定申告に対応するためには、まず確定申告の流れを理解することが大切です。
さらにしっかり帳簿を付けて事業所得の計算を正確に行える体制を整えるようにしましょう。 総収入金額や必要経費の計上にはそれぞれ理解しておくべきポイントがあります。
ほとんどの会計処理は会計ソフトを利用することで簡単に対応できますので、開業前から会計ソフト選びなど税務処理体制づくりの準備も進めておくとよいでしょう。
また、開業時には節税メリットが得られる青色申告者になるための手続きも行っておくことをおすすめします。 独立開業した個人事業主は確定申告書の流れとポイントを理解して確定申告にしっかり対応しましょう。
フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す ビジェント
オススメの商材・サービスを集めてみました!
-

お酒の美術館
-

地域密着型デイサ-ビス だんらんの家
-

レンスペ本舗
-

「はなまる造園」植木職人
-

IBJ
-
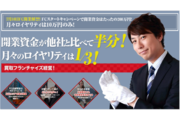
銀座屋
-

らあめん花月嵐
-

訪問鍼灸マッサージ「KEiROW」
-
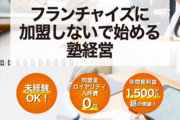
教育ICT「システムAssist」
-

就労継続支援B型事業所「スーパーチャレンジセンターミライ」
-

すらら塾
-

大石久右衛門
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015