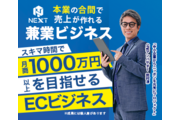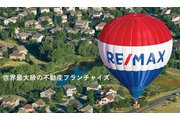居酒屋・バーの独立開業の届出に関する基礎知識

居酒屋やバーの経営を始めるには、様々な免許や許可手続きをクリアしなければなりません。
資金の調達や物件の選定、従業員の確保に広告活動など、開業前にやるべきことが山のようにありますが、法的な手続きでつまずかないために最低限どんな許可や免許が必要か、そしてそれをどんな方法でクリアしていくのがベストな方法かをしっかり知っておくことが重要です。
ここでは大まかに必要な手続きと資格について解説していきます。
1
食品衛生責任者
居酒屋やバーなどの飲食店では必ず必要になる資格が「食品衛生管理者」です。
この資格は食品を扱う業者の衛生の自主管理を目的としていて、飲食店の場合は必ず施設に1人の設置が義務付けられています。
通常は開業されるオーナーが取得することになるでしょう。従業員の衛生教育、施設の管理、食品の取り扱いの管理などについて各都道府県で行われる講習を受講して資格を取得します。
講習はだいたいどの都道府県でも6時間ほどで、1日の講習で取得できますので、飲食店の開業を考えている方は真っ先に取得しておきましょう。
受講料は各都道府県によって多少の違いがありますが、だいたい1万円ほどです。講習実施日は月に7回から8回ほど開催されています。
問い合わせは各都道府県の衛生課や保健所におこなってください。なお調理師や栄養士などの免許を持っている方は自動的に取得できますので講習を受ける必要はありません。
2
防火管理者
ビルや建物の万一の火災に備え、定期的に消防設備の点検整備や避難訓練の実施などの防災活動を中心になって行う人の資格で、収容人数30人以上の店舗の場合には防火管理者を選任することが義務付けられています。
延床面積が300平米未満の場合は「乙種防火管理者」、延床面積300平米以上の場合は「甲種防火管理者」の資格が必要ですが、個人経営の飲食店や最初に開業されるオーナーが必要になるのは「乙種防火管理者」の場合が多いでしょう。
「防火管理の意義と制度」「火災の現象」「消防用設備と建築防災施設」などについて各都道府県や市町村の本部で講習を受けます。
費用は3,000円から5,000円程度で乙種なら1日で取得できます。甲種の場合は2日間の講習で5年ごとに再講習を受けることが義務付けられています。
これとセットで「防火対象設備使用開始届」と「火を使用する設備の設置届」という届け出を所轄の消防署に提出しなければなりませんが、たいていは内装業者さんが届け出てくれる場合がほとんどです。
万が一届け出ていない場合があると法令違反になってしまいますので内装業者さんに確認しておきましょう。
3
調理師免許
よく勘違いされる方も多いですが、飲食店の営業に必ず必要とされる免許ではありません。調理師免許がなくても飲食店の営業は可能です。
ただフランチャイズ店でもない場合は調理師免許を持っていたほうが信用につながりますし、オーナーさんが持っていなくても調理する従業員には調理師免許を持った人がいた方がよいでしょう。
また調理師免許を取ると上述した「食品衛生責任者」の講習を受ける必要がありません。
ふぐ料理を提供する場合、都道府県によっては「ふぐ調理師」の免許が必須になる場合があるので注意してください。
調理師の資格は飲食店での実務経験が2年以上で、各都道府県で行われる試験を受けられます。
この試験自体の合格率は50%以上ですからそれほど難関試験というわけではありません。
なお調理師学校などの養成施設で1年以上訓練した場合は無試験で取得できます。食中毒の予防知識や専門的な料理の知識について学ぶことができるので、飲食店の経営のために取っておいて損はない資格です。
4
食品営業許可
さて、ここからは官公庁への営業許可申請となります。この許可申請が取れていないと飲食店の営業ができませんので開業準備中にしっかりプランを立てて準備してください。
もし面倒な場合は行政書士さんなどの専門家に任せてもよい手続きです。貴重な自分の時間を他のことに確保したいという場合は、外注するのもひとつの手でしょう。
その場合はそれぞれの専門家によりますが、だいたい高くても5万円程度で全ての手続きをしてくれます。自分で届け出をする場合は、まず最寄りの保健所に相談してください。
できれば内装工事の着工前に店舗の設計図を持参して相談にいくと良いです。保健所に事前に相談することで営業許可の要件とスケジュールがわかりますので、オープン前のトラブルを避けられることになるでしょう。
貯水槽や井戸水を使用する場合は「水質検査成績書」の提出が必要で、水道以外の水を使用する場合は水質検査を行う必要があります。
手数料はだいたい16,000円から20,000円で「営業許可申請書」「営業施設の図面」「食品衛生管理者などの資格を証明するもの」「水質検査成績書」などが主な提出書面になります。
そして届け出後に保健所からオーナー立会いの下で検査に来てもらわなければなりません。この検査をクリアして晴れて営業許可が下ります。
5
深夜酒類提供飲食店営業届
深夜0時から日の出までの時間にお酒を提供したい場合には必要になる届出です。これは警察署に届け出を行います。
手続き自体は複雑ですのでこの許可申請は専門家である行政書士に頼んだ方がベターです。その際は深夜営業許可申請を専門に行っている行政書士(風営法専門の行政書士)に依頼しましょう。
費用はそこそこかかりますが(ケースによりますが10万円前後)ここはオーナーさんの貴重な時間を大幅に節約できると考えましょう。
そこでオーナーさんは細かい申請手順の内容というよりは自分の開業する店で深夜酒類提供許可が必要か否かをおさえておく必要があります。
まず深夜営業のバーや居酒屋ではこの許可が必要です。そして例えばおにぎり屋さんを深夜に営業するとして、そこでおつまみにお酒を提供するという場合でも必要になります。
要するに深夜0時以降にお酒を提供するのならば飲食店のスタイルに限らずこの許可を取得しなければなりません。そしてもうひとつの注意点は、立地に制限があることです。
この類の店舗は、行政の決めた用途地域という行政区分の中でも商業地域、近隣商業地域、工業地域以外での営業は原則としてできません。
隠れ家バーだといってうっかり住宅街などに出店してしまうと違法営業になってしまいます。用途地域については各市町村役場の担当者に連絡してよく確認してください。
この他にも内装についての規制なども細かいので、この許可が必要な飲食店を開業する場合は、立地や内装の決まっていない段階で専門家や内装業者に相談してください。
6
まとめ
居酒屋やバーなどの出店で必要になる免許や許可申請について代表的なものを説明しましたが、この他にも個人事業の場合は「開廃業等届出書」を税務署に、従業員を雇う場合は「労災保険の加入手続き」を労働基準監督署に届け出なくてはなりません。
従業員を雇う場合はこれに加えて「雇用保険の加入手続き」(届け出先は公共職業安定所)と「社会保険の加入手続き」(届け出先は社会保険事務所)なども必要です。
個人事業主の場合は「社会保険の加入手続き」は任意なので加入していない場合も多いのですが、近年は国として社会保険への加入を強化している傾向があるので、余計なトラブルを避けるためにも加入手続きを行ったほうが無難です。
開業前のオーナーさんはいくつ体があっても足りないくらいやることが多いでしょうが、他人の力を使えるところはうまく使いながら、しっかり開業準備をしていきましょう。
フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す ビジェント
オススメの代理店・フランチャイズ・業務委託・副業を集めてみました!
-

顧客満足度No.1 / 浄水サーバー
-

女性専用ピラティス・よもぎ蒸しスタジオ「SOELU」
-

【公式】キャリアから直接募集!販売パートナー
-

リクルートのキャッシュレス決済【Airペイ】
-
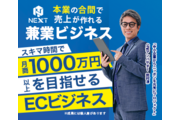
【月々約7万円で開業】兼業から独立可能なEC事業
-

「ラフテル」不動産仲介エージェント
-

軽貨物スポット便「スーパーカーゴ」
-
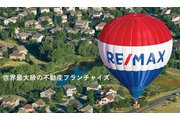
新しい不動産ビジネス「RE/MAX」
-

すしと酒-箔-
-

あなたの戸建てリストが宝に!営業不要の新手法
-

1件で報酬900万円の実績あり!不動産エージェント
-

お問合せフォームAI自動営業ツール【正規販売代理】
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015