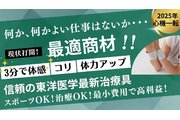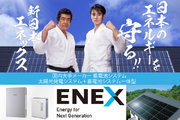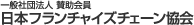印紙は必ず必要?代理店契約書の特徴と作成時のポイントについて

代理店契約書を用意する際は注意すべき点があります。
例えば、代理店契約書と販売店契約書を混合してしまうケースがよく見られます。
両者の違いを明確にしておかないと思わぬトラブルに繋がる可能性も。
また、代理店契約書を作成する際には印紙についての正しい知識も必要です。
本記事では代理店契約書の特徴や作成時のポイント、印紙などについて詳しく解説します。
1
販売店契約書とは違う?代理店契約書とは
代理店契約と販売店契約は言葉が似ているため混同されることが少なくありません。
しかし、この2つは異なるものです。
代理店契約を正しく結ぶためには両社の違いを理解する必要があります。
ここでは、それぞれの特徴を解説します。
1-1.販売店契約書の特徴
販売店契約書は販売店が商品・サービスをメーカーなどの供給者から仕入れ、自分の名前で顧客に販売するための契約書のことです。
販売店契約は特約店舗契約と呼ばれる場合もあります。
販売店は供給者と継続的な売買取引を行うため、契約書の様式は売買契約書に近い形になることが特徴です。
ただし、契約に際して供給者との間にさまざまな権利・義務の有無などを決めておく必要があります。
具体的には供給者の販売店への協力義務、商標権の利用、独占的販売権の有無、販売促進義務などです。
販売店契約を結んだ後、顧客と商品・サービスの販売契約を交わす場合、契約当事者となるのは販売店と顧客です。
契約者として供給者の名前は一切出てきません。
すなわち、販売に対する責任は全て自分が負うことになります。
顧客の代金支払いが滞った場合の代金回収や在庫を抱えるリスクなどは販売店が直接対処しなければいけません。
また、顧客からのクレーム対応なども同様です。
さまざまな部分で販売店に責任が発生するのでその点は理解しておきましょう。
1-2.代理店契約書の特徴
代理店契約書は販売代理店として商品・サービスの供給者と顧客の売買に関する仲介を行い、仲介手数料をもらう契約書のことです。
代理店契約は供給者から代理店に代理業務が委託されることから、業務委託契約に近い形と考えると良いでしょう。
顧客に商品・サービスを販売する場合、販売店と顧客の間で直接契約が結ばれる販売店契約と異なり、代理店契約ではメーカーなど供給者と顧客の間で契約が結ばれます。
代理店はあくまで供給者と顧客の仲介役であり、契約の当事者にはなりません。
そのため、顧客から代金回収できない場合のリスクや商品・サービスへのクレーム対応などを行う必要はなく、全て供給者の対応になります。
また、商品は代理店を介さず、供給者から顧客に直接渡される仕組みなので、代理店が在庫リスクに悩むことも基本的にはありません。
商品・サービスの売上から仕入れ額を差し引いた金額がそのまま利益となる販売店と収入の流れなども異なりますが、さまざまなリスクを回避しながら営業できることが特徴です。
2
代理店契約書作成時に押さえておくべきポイント
代理店契約書を作成においてはいくつかポイントがあるので押さえておきましょう。
まずは手数料についてです。
代理店契約書では、手数料の割合を具体的に決めることが重要になります。
手数料は代理店の収入になる部分です。
曖昧にしておくと後々供給者と揉めるもとになりかねません。
また、仲介にかかるコストや労力などをしっかり算定し、自分たちに必要な手数料がどのくらいなのか検討した上で契約書に載せましょう。
併せて、支払期日や支払方法いついても契約書に明記しておきます。
さらに、二次販売代理店への委託についても決めておくべきです。
例えば、契約で二次代理店への委託を認める旨を明記しないまま二次代理店を使うと、供給者に契約違反と見なされる可能性もあります。
なお、供給者は代理店に業務を委託している側として、代理店に成果や販売状況の報告などを求めます。
これを見越し、契約書の中において報告する内容などについて情報をまとめておくと良いでしょう。
その他、代理店の売上の低迷や方針の変更などにより、代理店契約が終了することもあるため、契約終了後の対応に関しても契約で取り決めておきます。
このように、さまざまなことを契約時に決めても、契約履行中に契約内容を変更しなければならないときもあります。
その際どちらかが一方的に契約変更をすることのないよう、契約変更に関する流れもあらかじめ定めておきましょう。
3
業務委託契約書に似ている?代理店契約書のフォーマット
代理店契約書を作成する上でのポイントはわかっても、実際作成するとなるとどのようなフォーマットが適しているのか迷ってしまうこともあるでしょう。
その場合は、業務委託契約書を参考にしてみてください。
代理店契約は業務委託契約と共通点が多いので、業務委託契約書をベースにすると作りやすいです。
また、契約書には、供給者の業務を代理店に委託する旨の文言が多くなります。
代理業務の具体的な内容や商品・サービスの販売方法、手数料の設定、支払方法など、代理店契約に必要な項目を記載しましょう。
4
7号文書が鍵!代理店契約で印紙が必要になる条件
契約書を作成する際、取扱いを考えなければならないのが印紙です。
代理店契約を結ぶ際に、契約書が印紙税法で定めるところの第7号文書に該当する場合、印紙が必要になります。
第7号文書とは、継続的な取引を行う際の基本的な契約書のことです。
なお、第7号文書以外にも印紙税法では1~20号までの文書を定めています。
例としては、不動産売買契約に関する規定を定めた第1号文書や請負に関する規定を定めた第2号文書などがあります。
第7号文書に該当する契約書は、営業者同士、つまりBtoBの取引や売買の委託を目的としている、売買の契約期間が3ヶ月以上、更新の定めがあるといった条件があるので覚えておきましょう。
なお、代理店契約書以外に、売買基本契約書や業務委託契約書なども第7号文書です。
第7号文書にあたる書類には、4,000円の収入印紙を貼り付ける必要があります。
5
払わないことも可能?印紙税の節約術
代理店契約書が第7号文書に該当する場合、印紙貼付の対象になります。
つまり、裏を返せば第7号文書に該当しなければ印紙貼付の対象にはならないということでもあります。
そこで、この段落では印紙税を法律の範囲内で節約するテクニックについて解説します。
5-1.委任契約や準委任契約にする
まず節約方法として挙げられるのは、契約の形態を工夫することです。
具体的には、代理店契約ではなく、委任契約や準委任契約とすることで第7号文書の条件から外すというものです。
印紙税法において第7号文書を規定する文言の中に「基となる契約が、売買、売買の委託、運送、運送取扱い、請負のいずれかに該当すること」と記載があります。
つまり、ここに挙げられている以外の委任契約や準委任契約であれば第7号文書には該当しないことになります。
委任契約と準委任契約は字面が似ており、同じような意味にとらえられることもありますが必ずしもイコールではありません。
委任契約は一方の契約者がもう一方の契約者に法律行為を委託する契約のことです。
また、準委任契約は法律行為ではない作業や事務などを委託する契約を言います。
委任契約書や準委任契約書は非課税文書なので印紙貼付の必要もありません。
ただし、委任契約や準委任契約であるかどうかの判断はやや難しい面があり、知識が曖昧な状態で作成すると不十分な書類になる可能性があります。
税理士などの専門家に一度相談したほうが安心かもしれません。
5-2.契約の期間や方法を工夫する
契約の期間や方法を工夫することで、第7号文書の条件から外すという方法もあります。
印紙税法における7号文書の規定には「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」と記載があります。
つまり、契約の期間を3カ月以内にし、かつ更新に関する定めを契約に盛り込まなければ第7号文書の条件から外れるということです。
期間や更新に関する部分の工夫はそれほど難しいものではないので、印紙の節約術として活用しやすいでしょう。
その他、第7号文書は2以上の取引を継続して行うものという規定もあります。
これを回避するため、複数の取引を含めた基本契約1本ではなく、基本契約の内容を含んだ個別契約を繰り返すという方法をとるのも有効です。
ただし、それぞれの取引に関し個別契約を結ぶことで契約の手間が増える可能性があります。
7号文書に該当しない契約書を作りたい場合は、契約相手と事前に相談し相手の了承も得ておくことが望ましいでしょう。
5-3.代理店契約書を電子契約書で用意する
代理店契約書を電子契約書で作成するのも印紙税を節約するためのセオリーです。
第7号文書の条件を満たさない契約書を作成することは印紙貼付を回避するためのテクニックの1つではあります。
しかし、内容によっては契約書の内容に無理や不自然さが出てくることもあります。
不自然なく契約書を作り印紙を節約したいなら、電子契約書で代理店契約書を用意するのが良いでしょう。
印紙税は書面に対してかかる税金なので、紙の契約書ではない電子契約であれば収入印紙は必要ありません。
電子契約書と言うと特別な作り方をしなければならないのではと考えるかもしれませんが、難しく考えなくても大丈夫です。
例えば、基本契約を結ぶときに、契約書をPDF化する方法があります。
PDF化はパソコン上でボタンを押すだけで可能なので、簡単に印紙の節約ができます。
ただし、収入印紙が必要ない電子契約書とは、あくまで原本をデータ上で取扱い、保管している状態のものを言います。
PDF化したものをプリントアウトして印鑑を押すなどすると、書面化したと見なされ収入印紙貼付の対象となってしまうので注意しましょう。
6
ペナルティは重い?印紙を貼付しない場合のリスク
7号文書にあたる代理店契約書には収入印紙が必要だと説明しましたが、もし印紙を貼付すべき代理店契約書に貼付をしなければどうなるのでしょうか。
この段落では印紙を貼付しなかった場合のリスクについて解説します。
6-1.事業者としての信用が低下する
印紙を貼付していないと契約書自体が無効になるのではと考える人もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。
印紙の貼付と契約行為・内容は別に考えるものです。
当事者間において契約をする意思表示さえしていれば、印紙税を収めていなくても契約自体は成立します。
印紙を貼付ないことで、契約が履行できず契約相手に直接迷惑をかけることはありません。
しかし、印紙を貼付しないことによって事業者として社会的な信用が落ちる可能性は否定できないでしょう。
印紙の貼付は法律で定められていることです。
印紙貼付は法律を遵守していること、すなわち健全な事業運営をしている証でもあります。
印紙を貼るべきにも関わらず貼らないというルーズな対応は、取引自体も誠実に行われないのではないかと、取引先に不信感をもたれることにも繋がりかねません。
このようなマイナスイメージを持たれないよう、代理店契約書を作成する際には必要な印紙を貼付すべきです。
6-2.過怠税の納付を求められる
収入印紙を貼付しないことによって、過怠金が発生するリスクがあることも忘れてはいけません。
代理店契約書が第7号文書など印紙を貼るべき書類に該当するにも関わらず貼らなかったということは法律違反です。
そして、発覚したときは法律通りの印紙を貼らなければならない他、税金を追加徴収されます。
この税金の追徴を過怠税と言い、過怠税は本来貼付すべきであった印紙の金額の2倍の金額が徴収されます。
合計すると元々の3倍の金額を支払う計算となり、大きな出費となります。
ちなみに、印紙は貼付した後、契約者の印鑑で消込しなければいけません。
例え正しい金額の印紙を貼っていたとしても消印をしていなければ過怠税の対象となるので注意しましょう。
なお、このケースの追徴額は印紙の額と同じです。
契約書類は自分たちで保管するものなので、印紙を貼らなくてもバレないだろうという考える人もいるかもしれません。
しかし、そのような考えはやめた方が良いでしょう。
税務署が事業者に税務調査に入ることは珍しくありません。
調査では事業者が保管している書類を全て確認されます。
もちろん契約書類も調査の対象です。
税務調査で印紙を貼っていないことが発覚し、一気にまとまった過怠税を徴収される事業者もいます。
このような事態は避けるのが望ましいでしょう。
契約書に印紙が必要な場合は誤魔化したり無精したりせず、適切に印紙貼付することが大切です。
7
まとめ
代理店契約書や印紙についてもっと知りたいときはビジェントへ
代理店契約書を作るには販売店契約書との違いを十分理解することが大切です。
代理店はさまざまなリスクを負うことなく事業を始められるメリットがあります。
また、代理店契約書は第7号文書に該当するため印紙も忘れず用意してください。
印紙税節約には本記事で紹介した内容が参考になるでしょう。
なお、代理店契約書や印紙などについてさらに詳しいノウハウを知りたい人は、ビジェントのホームページにアクセスしてみてください。
オススメの商材・サービスを集めてみました!
-

「ラフテル」不動産仲介エージェント
-

リクルートのキャッシュレス決済【Airペイ】
-

【外国語対応スタート】ライフライン契約代行サービス
-

超高額インセンティブ!個人法人通信ライフライン商材
-

【関東】インフラ営業協力会社募集
-

「サジェスト対策サービス」販売代理店募集
-

お問合せフォームAI自動営業ツール【正規販売代理】
-

顧客満足度No.1 / 浄水サーバー
-

次世代型AI翻訳機「okitalk(オキトーク)」
-

【大阪限定】専門知識無しOK賃貸紹介パートナー募集
-
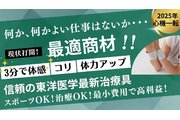
催事販売や訪問販売をされている方必見!成約率80%
-
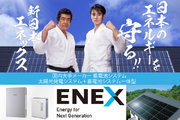
継続率トップクラス!太陽光発電・蓄電地・V2H販売
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015