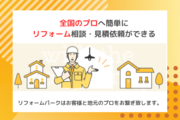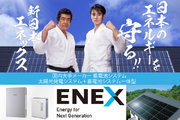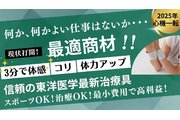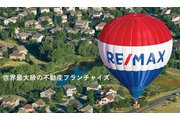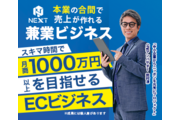オフィス開業について

オフィスを開業するにあたり、まず考えなくてはいけないのが、事業計画であるといえます。
それは、どんな業種・業態といえども共通している点であるといえます。
オフィスを開業するにあたり、どんな商売をどんなかたちでどうやって利益を出していくかの明確なビジョンがなければ、その先の成功はないといっても過言ではありません。
むろん、オフィス開業には、資金が必要です。
必要な経費として、商品やサービスの仕入れやテナントの賃料、従業員を使うのであれば、人件費などその額は想像以上に大きいとされます。
今までの預貯金ですべてまかなうことができるのであれば、それに越したことはありませんが、場合によっては、金融機関からの借入も検討しましょう。
資金の準備の見通しが立てば、後は、会社のネーミングやキャッチコピーです。
なるべくインパクトのあるものを考え、少しでもアドバンテージを得たいものです。
行政機関や業種によっては保健所などへの必要書類などの提出も忘れてはいけないところですので、行政書士に相談するなどしてしっかり対応しておかなければいけません。
オフィス開業の前には、物件選びが重要事項であります。
ほとんどの場合が、不動産業者を介しての契約になるものですが、その際には、信頼できる不動産業者を選ぶことが大切です。
これから始める業種に適している物件選びが重要です。
立地条件や周辺地域の人口構成、築年数など複数の要素を総合的に判断する必要があります。
会社の命運を握るといっても過言ではありませんので、しっかりとした物件を選びたいものです。
1
介護事業の開業手続きは慎重に
介護事業を開業したいと思った際には、慎重に行動しなければなりません。
ただ単に法人を開業すればいいだけではなく、介護保険法の規定やその認可にあたる行政庁、都道府県や市町村役場などに対して事前に相談をしっかりと行うことや、就業規則、法人定款等で守るべき事柄などの指示がなされますので、その指示に従って様々な書類等の準備が必要になるからです。
また、法人開業と同時に介護事業をスタートすることはできないことはありませんが一般的には難しいのが現実です。
したがって、法人開業後速やかに介護事業も認可となるように、体制の整備をはじめ人員の整理などを行う必要が生じます。
また、場所の確保も重要です。
実際に事業所内でほとんど介護を直接提供はしない居宅介護支援事業者、訪問介護事業等であっても、事務スペース等の確保などは求められるためです。
他のサービスであればなおのことサービス提供に必要な場所等は求められます。
こうしたルールは書類だけ形のみ用意すればいいものではなく、その提出した状況に変化が生じれば、変更届出を出さなければならなくなります。
したがって、書類だけの上辺のみを適当にごまかせばいいものではないことに注意が必要です。
指定や指導権限を有する行政庁によっては、開業後の実態の確認のために事業所を訪問するところもありますので、開業時に提出した書類と実態とが嘘だったということがないように、誤りなく実態に沿った書類作成を行うのは基本中の基本です。
2
資格を取得して士業として開業するには?
資格というのはいろいろありますが、それらを取得することで、そのまま仕事として生かせるものも多くあります。
その資格を取得することで、現在の給料にプラスの手当が出ることもありますが、それらを使って開業することも可能な場合があるのです。
特に難関試験と呼ばれている士業の資格を取得すると、試験に合格してすぐに開業することもできるかもしれません。
しかし、実際にはどういった仕事をするのかということや、どうやって顧客を獲得していけばいいのかなど、問題は多くありますので、資格を取得してすぐに開業するケースは少ないともいえるでしょう。
士業として開業しやすい職業として、弁護士や司法書士、税理士、そして行政書士などが挙げられます。
どの職業も、まずはそれらの事務所に勤めて、ある程度どうやって仕事をしていけばいいのかが分かってから独立開業をする順序が多いのではないでしょうか。
難関の資格試験を勉強するときは、予備校に通うということもあるので、そういった予備校で開業のための講座が開かれている場合もあります。
全ての資格で講座が開かれているわけでもありませんし、特定の資格の開業講座ということもあるのですが、こういった機会を利用していってもいいかもしれません。
自分だけでいきなり仕事を始めようと思っても、何から始めたらいいのか分からないことも多いですので、専門家のアドバイスも参考にしながら、これからどうやって仕事をしていったらいいのかを考えていくというのも一つの方法です。
3
公認会計士として独立開業するために必要不可欠な手続き
公認会計士として独立して開業し、業務を行うことができるようになるために必要不可欠な手続きは以下のとおりです。
先ず、金融庁が実施します国家試験たる公認会計士試験に合格しなければなりません。
この試験は、短答試験に合格し、その後論文試験に合格すると最終合格者となります。
しかし、試験に合格しただけでは、単に公認会計士試験合格者の地位に過ぎず、公認会計士の資格を有しておりません。
公認会計士の資格を取得するためには、さらに次の2条件を満たさなければなりません。
それは、2年以上の業務補助または実務従事、すなわち、2年以上の実務経験を積むこと、及び、日本公認会計士協会が実施します実務補修所の講義を受け、終了考査に合格するという条件です。
これらの条件を全て満たせば、公認会計士の資格を取得することとなります。
しかし、公認会計士と名乗り、独立開業して業務を行うためには、さらに、日本公認会計士協会に登録して会員になるという手続きが必要不可欠です。
そのためには、登録料を支払い、その後会費を支払い続けなければなりません。
以上の手続きを全て行えば、公認会計士と名乗り、独立して開業し、自分の公認会計士事務所を持ち、業務を行うことが出来ます。
しかし、実際に独立開業し、経営が上手く行くためには、得意先を確保するという手続きが必要不可欠です。
新たに得意先を確保することは容易ではありませんので、独立開業することを目指す場合、前もって得意先を確保できるかどうかの見通しを検討することが重要です。
4
安定した需要が見込める保険代理店ビジネスとは?
保険代理店ビジネスを開業するメリットの一つは、安定した需要が見込めるという点です。
インターネットプロバイダーサービスの販売や、携帯電話の販売は販売ターゲット層が一部の層に限られていますが、保険商品は老若男女を問わず加入需要があるので、幅広い層の客層をターゲットに営業を行う事が可能です。
また、保険商品は一度加入してからの契約期間が長いため、顧客との長い付き合いが期待できるというのもメリットの一つです。
保険に加入して頂いたお客さんとの付き合いを通じて、その顧客の親族であったり友人といった新たな顧客候補の紹介を受けられるケースが多いのです。
保険代理店を開業する第三のメリットは、初期費用がかからないという点です。
商品の紹介を行う為のパンフレットの作成や、代理店として営業している事を宣伝するための広告作成費など多少のコストは発生しますが、商品販売のパンフレット等は商品の販売元である保険会社が用意したものをそのまま使えば良いというケースも多いため、開業に際して高額の初期投資を行う必要が無いのです。
しいて準備する必要があるといえば、販売する商品に関する知識や、金融に関する基本的知識を習得しておく事でしょう。
また保険の代理店は複数の企業の商品を一度に取り扱う事が可能であるため、その時々の売れ筋商品を前面に出して営業を行えば、商品が売れずに困るという事はまずありません。
一つの商品の販売手数料も高いので安定した収入を期待することが出来ます。
5
携帯電話の代理店募集・加盟店募集(中古買取、au、NTTなど)
各携帯電話会社の費用やシェアを比較することで、その会社の特徴をつかめます。
例えばSoftbank(ソフトバンク)のiPhoneは、スマートフォンにおいて非常に大きなシェアを持っています。
デザインも洗練されており、学生ならば学生プランを使うことで安く使用できます。
一方、Androidもますますシェアを伸ばしています。
AuとDoCoMoは次々に新機種を導入しており、市場争いが日々繰り広げられています。
機種が充実しているので、自分に合う携帯を選べます。
実は弊社も携帯電話の正規販売代理店を行っております。
乗換応援をおこなっているので、興味がある方は「携帯百貨店」で検索してみてください。
オススメの代理店・フランチャイズ・業務委託・副業を集めてみました!
-
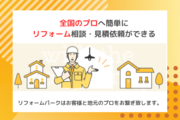
商談設定のみ|「リフォームパーク」紹介店募集
-
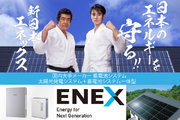
継続率トップクラス!太陽光発電・蓄電地・V2H販売
-

大石久右衛門
-

超高額インセンティブ!個人法人通信ライフライン商材
-

「ラフテル」不動産仲介エージェント
-
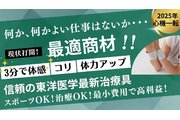
催事販売や訪問販売をされている方必見!成約率80%
-

個別指導WAM(ワム)
-
高インセンティブ!高アポイント!「地域創生でんき」
-
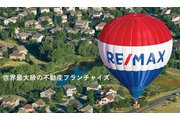
新しい不動産ビジネス「RE/MAX」
-

次世代型AI翻訳機「okitalk(オキトーク)」
-

【家計相談】ライフプランニングの顧客紹介
-
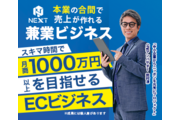
【月々約7万円で開業】兼業から独立可能なEC事業
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015