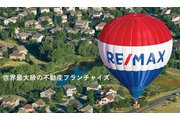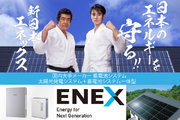開業における資金計画のコツ

開業において、多くの人がつまずく理由の一つに資金不足があります。
大丈夫だろうという見通しのもとで始めた事業が予想以上にうまくいかず、生活が苦しくなり事業のための資金を切り崩しながら生活していく中でどうしようもなくなって廃業してしまったというパターンも決してありえない話ではありません。
こういった資金不足に陥る原因は起業時の資金計画が甘かったことにあります。
開業するうえで、今の生活水準を極端に落とすことはしなくても何とか生活はできるという前提のもとで資金計画を組む人もいますが、これは間違いです。
事業を始めたからといって、その事業がすぐに日々の生活をしていくのに十分な売り上げを出す保証はありません。
日々の生活のために十分な利益を上げられるようになるのが、半年後になるのか、1年後になるのか、あるいはもっと先になるのか、そういったことまで想定して、そのための生活資金も補填できるだけの資金があってこそ安定した企業ができるのではないかと思われます。
企業の失敗は廃業だけでなく、多大な借金を背負うことになるかもしれないリスクを負うことになります。
安易な資金計画では、自分だけでなく、家族や友人などの自分に近しい大切な人たちにすら迷惑をかけることになるかもしれません。
開業するうえで大切なのは遠く先の最悪の状況すらも想定した資金計画を持つことです。
事業がうまくいかず、日々の生活も困難になり、それでも生活分の資金を補うことができるほどの十分な資金を用意していくことこそが最善の資金計画と言えます。
1
開業の助成金について調べてますか?
様々な事業を開業すると、その地域の地方自治体や厚生労働省などから助成金を受けられることがあります。
どのような事業でも条件を満たせば受けられる助成金、たとえば雇用関係などの人員確保のための助成金などがその代表例です。
地方自治体からも受けられる助成金がありますが、開業する場所の自治体ごとで変化するものもあるため、できれば開業前にあらかじめその地域でどのような助成金が受けられるのか調べておいて、その窓口などで確認をしておくのがよいでしょう。
もし、こうした役所などとの折衝などが面倒な場合には、社会保険労務士などに依頼して、助成金申請のための書類の代理作成や、その申請自体も引き受けてくれるところもありますので、依頼してみるのも一つの方法です。
事業を始める上でネックになるのは、特に個人事業の場合などではその運営資金です。
すぐに売り上げがあるなど経営が軌道に乗ればいいのですが、実際にはなかなか難しい面もあります。
介護事業などの新規参入が多いわけですが、こうした介護事業に関しては、サービス提供から収入になるまで時間がかかる場合があり、特にその間の経営が厳しくなる場合があります。
手持ち資金が余裕があれば別ですが、そうでない場合なども含めて、助成金が受けられるのであれば申請したほうが良いでしょう。
なお、こうしたものを受けるためには、そのほとんどが期間が決められていますので、準備は念入りにしておいた方が無難です。
2
開業資金とは事業を始めるための資金だけではありません
開業資金といった言い方をすると、事業を始めるために必要資金のことをいうように聞こえる方もいるかもしれませんが、開業資金とは事業を始めるための資金だけでなく、事業を始めた後もその事業の経営を維持し、さらには事業者が日々の生活を過ごすための生活資金も含めてこその開業資金としたほうが事業が安定するかもしれません。
多くの人が開業後に直面する問題が、事業を始めたはいいが経営が思うようにいかず、日々の生活も苦しくなっていくというものです。
こういった問題が発生する原因の一つには、開業時の資金計算の見通しが甘かったというものが考えられます。
事業を始める方の中には、開業計画の際に現在と同じ程度の生活水準を維持できるだけの売り上げが見込めることを無意識に前提として資金計画を立ててしまう人もいます。
しかし、起業とは最悪の場合やより悪い状態を考えて、それに備えたほうが万が一の時にも安定するものです。
事業を始めても必ずしも生活資金を十分に確保できるかは分かりません。
そのため、開業資金を用意する際に、事業を始めるのに必要なお金だけでなく当面の事業を維持するための資金や当面の生活を維持するための資金も計算したうえで用意する方が安定して開業することができると言えます。
もちろん、事前に用意できる資金が多いに越したことはありませんが、用意できる資金にも限界はあります。
始める事業がどの程度の売り上げを、どのくらいの期間で上げられるか。
そういった見通しも含めて、開業資金を用意するには様々なことを考慮した計画が必要になるのではないかと考えられます。
3
開業資金に充てる助成金申請について
独立して一国一条の主を目指すビジネスマンにとって、一番大変なことの一つが開業資金や運営資金でしょう。
独立開業に向けての開業資金は、自前で調達する方法がありますが、それ以外にも実は開業にあたっての助成金を受けられるケースがあります。
この独立開業資金関係で、たとえば従業員を雇用する関係でも助成金はありますし、さらに開業後介護保険関係の事業所であったりあるいは障害者総合支援法関係の事業を立ち上げる際の雇用に関する費用について、その一部などを助成することで独立後の安定した事業運営に役立ててもらいたいという主旨で設けられている助成金が存在します。
こうしたものは、調べてみないと分からなかったり、あるいは地方自治体の中ではそういった支給可能な助成金があるにもかかわらず、教えてもらえなかったりするケースがあり得ます。
つまり、申請する側がしっかりと情報収集する必要があるということです。
もし、開業時における事業関係で助成金等が支給されるものかどうか分からない場合には、思い切って外部の専門家に相談するのも手です。
社会保険労務士の中には独立開業時の助成金申請などで詳しい人もいますので、探してみて依頼するのも一つの方法でしょう。
この方法の最大のメリットは、面倒な役所への提出書類の作成代行が可能な場合が多いことと、申請のし忘れもらい損ねがなくなるということ、さらに社会保険労務士などを通じて人脈も形成できる可能性があるということです。
4
開業資金の融資について
元首相である安倍晋三が、アベノミクスでデフレ脱却として取り組んだ政策により、昨今は円安ドル高、株価上昇等、インフレ基調にあります。
引き続き地域創生など、日本経済を活性化する要因として注目される日本に拠点を置く日本企業の中で99%を占める中小零細企業に大きな期待が寄せられております。
今まさに、企業に向けて追い風のある絶好のタイミングなのです。
では、いざ起業しようとしたとき、どのような問題が生じるでしょうか。
人材やお取引の企業を見定めるのも大切なことです。
しかし、それらは会社が会社として成り立った時点で問題になることです。
まずは、企業の資金として、開業資金を調達する必要があります。
1円から起業できる日本ではありますが、会社で事業を行うためには膨大な資金が必要となります。
その資金の出元は、自己資金や知人から借りるという手段もありますが、一番手っ取り早いのは銀行から開業資金を借り入れる、つまり融資の手続きを受けることです。
経済が好調に推移する今日ですが、銀行はバブル期崩壊から問題視された不良債権により、貸し渋りが激しくなっております。
メガバンクといわれる都市銀行は元より、地元の中小企業を応援する立場である地方銀行すら容易には融資を承諾してくれません。
そこで注目されるのが、信用金庫や信用組合です。
これらは、比較的容易に融資をしてくれます。
また、今は起業をターゲットとしたファンドもあるようです。
5
自己資金0円でも社長になれる
独立して自分の会社を持ちたい、社長になりたいと考えた際にネックとなるのが、開業資金の問題でしょう。
現在は会社法の改正により資本金0円でも株式会社が設立できたり、法人格をもたなくても個人事業主として独立する場合には自己資金は不用となります。
しかし、起業はできても自己資金が全くの0円では、通常では商売をはじめることができません。
では、開業資金が用意できない人の場合には、どうしたら良いでしょうか。
フランチャイズや代理店などの募集をかけている会社の中には、加盟店登録費用や保証金の必要がなく取引がおこなえるものもあります。
希望する職種の会社のビジネスパートナーとなり、売上金額の何パーセントかをロイヤリティーとして支払えば良いので、開業当初の金銭的負担は一切ありません。
登録後の自分の働きにより、得た利益を会社のボリュームにすることができるのです。
もちろん、開業資金が不用なフランチャイズや代理店募集の会社でも、取引や業務に関するサポート内容は、保証金を必要とする会社に比べてもひけをとる事はありません。
黙っていても登録費用で稼げるような会社と違い、代理店の売上が自社の利益にもつながるため、むしろサポート体制は手厚いことが考えられます。
インターネットの独立支援サイトなどで、各種フランチャイズ募集などの案件も確認することが出来ますので、独立起業をお考えの方はいろいろとチェックして、自分にはどんな業種が向いているかを比較してみるのはいかがでしょう。
6
開業資金の借り入れとは?自己資金少なく開業するテクニック
サラリーマンを辞めて一念発起して独立開業する人は少なくありませんが、独立開業に際して最初のハードルになるのが開業資金の準備です。
開業にあたって必要となる資金の金額は始めようとしているビジネスの業種や形態(フランチャイズなのか完全自主開業なのか)によって異なりますが、数百万円単位の資金が必要になるケースは少なくありません。
独立するとサラリーマン時代のような安定した給与所得はなくなるため、少しでも多くの資金を手元に残しておきたいと思う人が多いと思いますが、そのような人は銀行などの金融機関から開業資金の借り入れを行うと良いでしょう。
金融機関から開業資金の調達を行う事ができれば、手元にある貯金に手を付けずにビジネスを開始する事も可能です。
但し、金融機関もビジネスで融資を行っている為、誰にでも無条件で融資を行ってくれるわけではありません。
開業資金の借り入れを行う為には、そのビジネスを営む事により利益が生じ、その利益によって融資の返済が行えるという事を、金融機関に対してプレゼンテーションする必要があります。
開業資金の融資に適用される金利レートは、金融機関が融資実行前に行う審査によって決定されます。
開業後に利益を生み出す蓋然性が高いと判断される場合には、低い金利レートが適用され、逆にビジネスが利益を生むかどうかに不安が残るという場合には高い金利レートが適用される傾向があります。
有利な条件で借り入れを行う為には、しっかりとした事業計画書等の準備が必要になるのです。
7
開業資金調達のために知っておくべき公的制度とは?
新規に事業を始めようとする場合には、それなりの開業資金が必要になります。
開業に向けて自分で資金を貯めていたとしても、それですべてを賄うことが難しい場合もありますし、すべての資金を使ってしまうと何かあった場合に身動きがとれなくなります。
そのため開業資金を借入金で調達するのが一般的です。
この資金調達に使える公的な制度があります。
特に、日本政策金融公庫が行っている国民生活事業の新規開業資金の制度は知っておくべきでしょう。
概略としては、新規開業資金の融資制度を通じて、新規開業や開業後7年以内の人に融資が行われるというものです。
開業する業種に対して少し要件があります。
それまで勤めていた会社の業種と同じ業種での開業や大学で専攻したことと密接につながりのある業種での開業といったものが主な要件です。
融資限度額は7200万円となっていますが、そのうち運転資金については4800万円までという制限があります。
また、返済期間については、運転資金は6か月以内の据え置き期間を含め5年以内となっていますが、設備投資についてはもう少し長い15年以内です。
こういった公的融資は低利で資金調達ができることも魅力ですが、要件さえしっかり満たしていれば融資を受けられる可能性が非常に高いこともメリットです。
普通に金融機関の審査を受けるよりは審査条件は有利になっていますので、資金調達の必要がある場合は、積極的に検討してみる必要があるでしょう。
8
開業費は繰り延べ資産として償却できます
開業費(創立費・設立費)は、繰延資産として、5年間にわたり償却することができます。
登記費用(印紙代等)や、会社の印鑑(実印・認印)等を、開業費として計上することができます。
会社の印鑑等は、事務用品で処理することもできます。
繰延資産は、預貯金・売掛金等の流動資産や、土地・建物等の固定資産とは別物であります。
開業費とか当初に払った経費を、複数年にわたり、均等に経費計上するのに用います。
たとえば、開業費が10万円とした場合、5年間にわたり、毎年2万円ずつ、償却していくとの考えです。
1年目に償却できるのが2万円のみなので、残りの8万円は、すでに支払い済みですが、貸借対照表には残るので、繰延資産という項目を別に設けて処理するかたちとなっています。
事業規模にくらべて少額の場合や、開業費の総額が概ね10万円以下の場合は、一括で処理をしても、税務署から指摘を受けることは、ほとんどありません。
赤字の場合は、繰越損失で対応できますので、開業費全額を処理することができます。
副業とか本格的でなければ、5年間の場合、手間がかかりますので、一括で処理する方法をお勧めいたします。
5年間の場合は、均等割りになりますので、途中で償却金額を増減することはできないので、計画を立てて対応することが必要です。
その他の、繰延資産としては、開発費も5年間にわたり、経費計上することができますが、これも事業規模や、利益の兼ね合いで、償却期間を検討してください。
9
開業直後の資金繰りを乗り切るために活用すべき開業費の減価償却
独立開業してすぐに収益が安定し、企業の資金繰りに余裕が出るというケースは稀であり、多くの起業家は独立直後の収益が安定しない時期に資金繰りに苦労する事になります。
特にフランチャイズ制度などを利用せずに独立した起業家は、売上げが安定するまでの期間が最も苦しい時期であると言えるでしょう。
こうした苦しい時期の資金繰りを少しでも軽減するために是非活用したいのが開業費の減価償却制度です。
これは開業時に必要となって購入した固定資産(店舗不動産やオフィス機器等)の購入費用を損金算入する事によって、税金負担を軽減するというものです。
通常、企業に課せられる法人税は企業が計算期間内に売り上げた収益の多寡によって決定されます。
例えば、計算期間内の売上げが100万円で税率が40パーセントという場合、法人税は40万円という事になります。
しかし、開業費の減価償却を活用すればこの法人税を軽減する事が可能なのです。
例えば開業費に1000万円かかっていて、毎年50万円までの減価償却が認められている場合には、制度を活用すれば課税所得は通常100万円のところ50万円となるので、法人税は20万円で済むのです。
こうした税制度をうまく活用すれば苦しい資金繰りの助けとなります。
減価償却として損金算入が認められる金額は、開業費の種類やその資産の性質によって異なりますので、一概にどれぐらいの税金が節税できるとは言えませんが、専門知識を持つ税理士に相談をすれば、資金繰りの効率化を図る事が可能です。
10
個人事業主がお店を開店させる際に掛かる費用
個人事業主がお店を開店させる費用は、何かと多く掛かります。
まず、お店を開店させる場所を自店舗で行うか借りるかによって随分違いが出ます。
自店舗であれば、保証金や家賃が掛からず、改装資金のみが必要となり、毎月の負担が軽減できます。
賃貸として借りる場合で改装を伴う場合、毎月の家賃の10か月から12か月の保証金が必要となります。
これは、万が一、家賃が滞納する場合や廃業などで撤退資金がない時に充てる費用であるため、契約事項通りの撤退となればすべて返金されますが、入居時には必ず必要な費用となります。
次に設備費用で、飲食店舗の場合であれば、冷蔵庫やガス器具を含めた水回り厨房機器、空調設備などです。
賃貸店舗であれば居ぬき物件を利用すれば、費用が少なく済みます。
空調や厨房器具、トイレなどがそのまま利用できる店舗を探せば費用を抑えることが出来ます。
自店舗であればすべてに費用が掛かりますが、家賃に回す費用を返済などに利用できることからメリットが高いです。
意外にも掛かる費用が店内の備品で、お店の中のメニュー表や食器類、レジ、のれんや傘立てなど細かなものすべてを揃える必要があります。
パソコン、インターネット環境、電話(FAX)などを揃えるだけで10万円以上が掛かります。
低く見積もっても1000万円から1500万円の開業費が掛かると言われており、個人事業の場合であれば自治体の制度融資を利用し開業費に充てることが負担が少ないと言われています。
11
開業費の償却について知っておくべきこと
独立して開業しようと考えている方も多いかと思いますが、ただ努力して儲けを出せばいいというものでは無いのです。
いざ事業を開始した場合、利益の計画というものは非常に重要になってきます。
具体的には利益を計上しすぎれば税金の負担は増え、少なすぎれば金融機関等からの資金調達は困難になってしまいます。
では開業後一定期間利益を平準化する良い方法はないでしょうか。
一つの案として任意償却の繰延資産を活用した利益調整という手段があります。
利益調整と聞くと何だかやましい響きがありますが、全く合法で税法に則った方法です。
繰延資産は原則は5年間均等償却が求められておりますが、任意償却の繰延資産は任意に、つまり自由に費用化ができます。
単純に言えば、儲かりすぎた年度に多く償却することも自由にできますし、利益が出ない年度には費用化せずそのまま資産計上したままにすることができます。
5年間の縛りもなく、いつまでも資産計上しておくことも可能なのです。
ではどのような費用が任意償却の繰延資産に該当するのでしょうか。
必ず発生し、かつ金額もそこそこのものになる開業費がまず挙げられます。
開業費は会社設立から営業開始までに発生した費用のことをいい、事務所の賃料や従業員の給与、水道光熱費や広告宣伝費など、更には発起人への報酬までとかなり広い範囲の項目が計上できます。
したがってかなりの金額を開業費として繰延資産計上できますので、これを上手に活用するのです。
このような方法で合法的な利益調整を是非してみてください。
12
開業費は償却期間にわたってメリットがある
開業費は会計上、5年以内の償却が認められています。
そもそも、開業費というと費用として認識されるかもしれませんが、実はこれはれっきとした資産なのです。
この資産を、償却期間にして5年間均等償却することで費用処理をすることが可能となっています。
費用処理としてのメリットは、やはり利益を少なく見せることが可能な点でしょう。
費用として計上されれば自ずと利益も少なくなります。
法人税などは利益を基に算出されますから、結果的に支払うべき税金が少なくて済むようになっているのです。
また、税務会計上はいつでも、開業費は損金算入することが出来ます。
償却期間は5年と言いましたが、税務会計上はいつでも好きな金額だけを損金算入することが認められています。
ですので、一番大変な時期であろう開業始めの時期に、開業費を全額損金算入させて開業費分だけ赤字を発生させて法人税を小さくすることが可能です。
逆に、利益がたくさん始めた時期に、法人税を節税したい場合は開業費を利益が出始める時期までに温存することも可能です。
メリットがたくさんある開業費の償却ですが、しっかりとタイミングを見計らって損金参入させなければいけません。
収益が上がっておらず現金収入も少ない時に損金算入させてもあまりメリットはありません。
収入が徐々に上がってきているというここぞのときに損金算入すべき費用です。
ただし、償却期間は5年以内ですので注意して活用をしましょう。
13
個人事業主は知っておいた方がいい開業費と任意償却
個人事業を開業する場合には、その準備にも経費がかかります。
当然、開業前に支払う必要が出てくるものもあるでしょう。
こういった費用については、まだ開業前であるため、帳簿に記入して普通に経費として処理することができません。
しかし、最終的に経費にすることはできますので、しっかり領収書を保管して集計しておきましょう。
そして、開業日になったらこれらの開業前の支出を処理することになりますが、一旦「開業費」と呼ばれる科目で処理をする必要があります。
これは繰延資産と呼ばれるものの一つで、支出の効果が将来の事業期間全体に関わるものであるため、理論的には事業期間すべてに均等に按分して経費化すべき性質の支出です。
しかし、現実に全事業期間を特定することはできませんので、5年以内の定額法による償却を行うのが原則となっています。
つまり、開業費が100万円だった場合には、初年度から毎年20万円の必要経費計上になるということです。
しかし、この開業者の償却は任意償却です。
ここでいう任意償却は、償却しなくても良いという意味もありますし、いついくら償却してもいいという意味も込められています。
そのため、初年度はほとんど利益が出なかったので、開業費の償却はやめておこう、3年目に利益が大きくなったので開業費の全額をここで一気に償却してしまおうということも可能なのです。
節税にもつながる可能性がありますので、開業費の任意償却については理解しておくことをお勧めします。
14
開業費の範囲、正しく理解できていますか?
開業費というのは事業を始めるために必要なお金だけを指したものではありません。
その費用の範囲は起業に必要な資金はもちろん、開業した後の当面の経営に必要なお金や経営が軌道に乗るまでの間の生活費なども含めたうえでの開業費と考えたほうが安定して事業を行えるようになるといえるかもしれません。
起業後、多くの人がぶつかる壁は起業したはいいものの事業の売り上げが思いのほか伸びず、経営以前に自分自身の日々の生活のためのお金が足りなくなってしまうというものです。
こういったことの原因として、事業を始める際に無意識のうちに日々の生活の費用を用意できるということを前提としてしまうというものがあります。
事業を始めてすぐに事業を経営していくのに必要な資金と日々の生活に必要な資金の両方を用意できるかどうかは分かりません。
もちろん、経営が軌道に乗れば生活のための費用も十分に用意できるようになるのですが、開業してすぐに経営が軌道に乗り、十分な売り上げをあげられるとは言い切れません。
企業というのは失敗すると取り返しのつかないことにもなりえるものですので、経営を進めていくうえでの計画は常に最悪を想定したものであるほうが安定します。
最初に用意する開業費を当面の生活費や当面の経営資金などの広い範囲で用意しておけば、起業後すぐには経営が軌道に乗らなかったとしても余裕をもって事業を行うことが可能になります。
こういった理由から開業費を用意するのならば、より広く遠くを見据えた計画を立てて資金を用意したほうがよいと言えるでしょう。
オススメの代理店・フランチャイズ・業務委託・副業を集めてみました!
-

女性専用ピラティス・よもぎ蒸しスタジオ「SOELU」
-
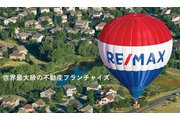
新しい不動産ビジネス「RE/MAX」
-

就労継続支援B型事業所エンターテインメントアカデミーでじるみ
-
高インセンティブ!高アポイント!「地域創生でんき」
-

顧客満足度No.1 / 浄水サーバー
-

株式会社ベアーズ
-

本格的リペア革・アルミ・木工修理等「ワールドリペア」
-

リクルートのキャッシュレス決済【Airペイ】
-
大手光回線卸しモデル(NTT回線以外)
-
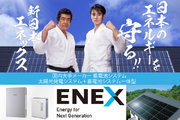
継続率トップクラス!太陽光発電・蓄電地・V2H販売
-

お酒の美術館
-

【関東】インフラ営業協力会社募集
まずは資料請求してみませんか?もちろん無料です。
(簡単な会員登録が必要です)
資料請求してみる





 0120-536-015
0120-536-015